相続の訴求範囲(=誰にどう関係してくるのか、どんな場面で注意が必要か)は、思っている以上に広いです。単に「人が亡くなったとき」だけではなく、意思能力が不十分になる前後の状況でも重要になります。以下にわかりやすく例を交えて説明します。
【1】死亡:基本的な相続の開始タイミング
- 例:父が亡くなった → 父の遺産(家、預金、借金など)を、配偶者と子どもたちが相続。
- ポイント:死亡時点で相続は発生。遺言書の有無で分け方が変わる。
【2】相続放棄・拒否
- 例:親が多額の借金を残して死亡 → 相続人(子)は「家庭裁判所で相続放棄」を申し立て。
- ポイント:死亡を知ってから「3ヶ月以内」に放棄手続きが必要。放置(ほうち)すると自動的に相続することになる。
【3】認知症(意思能力の低下)
- 例:母が認知症になり、財産の管理が困難 → 相続対策(遺言書作成や不動産売却)が難しくなる。
- ポイント:判断力が落ちた後は遺言や贈与が無効になる可能性あり。元気なうちの対策が大切。
【4】要介護状態・入院中
- 例:父が入院中・要介護で、自宅の売却や相続準備ができない。
- ポイント:
- 任意後見制度や家族信託を使えば対応できる。
- 相続人が施設入居費を肩代わりしても「相続分に影響しない」ため、不公平感が生まれやすい。
【5】相続人が行方不明・音信不通
- 例:兄が何十年も連絡が取れない → 他の相続人が手続きを進められない。
- ポイント:家庭裁判所で「不在者財産管理人」や「失踪宣告」の手続きを取る必要あり。
【6】再婚・非嫡出子・認知された子
- 例:亡くなった父に、認知した子がいた → その子にも法定相続権がある。
- ポイント:家族が知らない相続人が出てくる可能性がある。遺産分割協議に全員の同意が必要。
【7】相続発生後に遺品整理・家の管理を始めたら…
- 例:遺品整理のために家に入ったり、口座からお金を使った → 単純承認と見なされ、放棄できなくなる。
- ポイント:相続放棄を考えるなら「何もしないこと」が大切。安易に動かない。
【まとめ:相続に関わるタイミング】
| 状況 | 関連する相続行為・注意点 |
|---|---|
| 死亡 | 相続発生、遺言執行、遺産分割、放棄 |
| 認知症・要介護 | 遺言無効の可能性、信託や後見制度の検討 |
| 入院中 | 費用負担、財産管理、事前の対策が重要 |
| 借金がある | 放棄手続きを検討、債務の承継注意 |
| 相続人不明・多数 | 手続きが長期化、法的手続きが必要 |
| 再婚・認知 | 見えない相続人、トラブル回避の準備を |


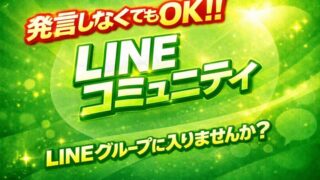






コメント