【1】「相続放棄」「遺贈の放棄」「遺言の放棄」の違い
■ 相続放棄(そうぞくほうき)
- 意味:相続人が「一切の財産を受け取りません」と家庭裁判所に正式に申し出ること。
- ポイント:
- 相続開始(通常は死亡)後3か月以内に家庭裁判所に申立てが必要。
- 財産(プラスもマイナスも)一切受け取らない。
- よくあるケース:
- 借金が多いとき(マイナスの遺産が多い場合)
- 親族関係が疎遠で関わりたくないとき
■ 遺贈の放棄(いぞうのほうき)
- 意味:遺言で「この人に〇〇をあげる」と書かれていても、その人が受け取るのを断ること。
- ポイント:
- 相続人でなくても受け取れるのが「遺贈」。
- 断るときは家庭裁判所ではなく、遺言執行者や相続人に意思表示するだけでOK。
- よくあるケース:
- 固定資産税など管理が大変な土地をもらいたくないとき
■ 遺言の放棄(※法律上の正式な用語ではないが…)
- 意味:遺言で指定された内容を、相続人が受け入れない、従わないという意味合いで使われることがある。
- ポイント:
- 正確には「遺贈の放棄」や「特定の条件を尊重しない」という意味に近い。
- 一部の遺言が不合理な場合、相続人全員の合意で遺産分割協議を別途行うことも可能。
- よくあるケース:
- 遺言の内容が古くて現状に合っていない場合
【2】遺産分割協議をやり直す必要があるケース(具体例)
■ ケース1:相続放棄した人がいたのに含めて協議した
- 例:Aさんが相続放棄したのに、協議書にAさんの署名がある。
- → 無効の可能性あり。やり直しが必要。
■ ケース2:後から相続人が判明した
- 例:亡くなった人に認知していない子がいて、後から戸籍調査で判明した。
- → その人を含めた再協議が必要。
■ ケース3:遺産があとから見つかった
- 例:協議後に預金口座や不動産が出てきた。
- → 新しく見つかった財産についての協議が必要。
■ ケース4:協議内容が不公平・強制だった
- 例:一部の相続人が他の人をだまして協議書に署名させた。
- → 無効になる可能性があり、再協議に。
■ ケース5:遺贈を受けた人が放棄した
- 例:遺言でBさんに土地をあげると書いてあったが、Bさんが受け取りを拒否。
- → その土地を誰に分けるか再協議が必要。


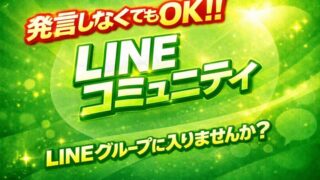






コメント