美大生が活躍できて、なおかつ他の参加者(高齢者や外国人留学生)とも交流できるイベントを企画します。
【イベント名】
「アートでつながる日曜日」 〜描いて、つくって、話して〜
【内容】美大生が主役になれる企画3本立て
①「あなたの似顔絵描きます!」(15分/人)
- 美大生がその場で高齢者や留学生の似顔絵を描く
- 描かれた人には絵をプレゼント
- 簡単な会話をしながら「あなたらしさ」を表現
美大生の活躍ポイント:観察力・表現力・コミュニケーション力を発揮できる
②「アート体験ワークショップ」
例:
みんなでちぎり絵や折り紙を貼って、大きな1枚の作品を完成させる。
- 美大生の活躍ポイント:先生役になれる!アートを教える体験ができる
- テーマ例:「ふるさとの風景」「未来の町」「みんなの笑顔」
- ポイント:色紙や雑誌を使って貼るだけなので誰でもできる
- 完成したら壁に展示 → 写真映えして記念にも!
- 美大生が「構成の下絵」や「貼り方のアドバイス」を担当
カラフルうちわ作り
- 内容:
無地のうちわに、シール・スタンプ・ペンなどで自由にデコレーション。 - ポイント:
・夏場にぴったり、持ち帰って使える!
・刃物・のり不要、貼る・描くで完結
・美大生がアートのお手本を見せると盛り上がる
③「ミニ展示&トーク」
- 美大生の作品を小さく展示(ポートフォリオや小品)
- 希望者は「この作品は○○の思い出から生まれました」など語る時間を設ける
高齢者や留学生:若い感性に刺激を受ける
美大生:自己表現の場・発表の練習にも!
【開催イメージ】
- 会場:地域の公民館、空きスペース、カフェ併設ギャラリーなど
- 所要時間:2〜3時間(1日イベント)
- 参加者数:15〜30人くらいが理想(密になりすぎない)
【参加料金の目安】
※材料費・お茶代・場所代に応じて柔軟に設定を。
【おすすめポイント】
- 美大生の才能を「直接体験できる」=来場者の満足度が高い
- 一方的な発表じゃなく「対話型」なので、自然な交流が生まれる
- 成果物(似顔絵・作品)が持ち帰れるのも嬉しい
異なる世代・文化の人々が交流する場はとても意義深いですが、円滑に運営するためにはいくつか注意点があります。以下に、高齢者・美大生・外国人留学生が交流するイベントにおいての注意点と、文化・人種によって起こりやすいもめごと例を挙げます。
【開催にあたっての注意点】
1. 言語の壁への配慮
- 通訳や簡単な多言語案内(英語・やさしい日本語)を用意。
- アイコンやイラストを使ったサイン表示も有効。
2. 文化的な違いを尊重する姿勢の促進
- ジェスチャーや表現が誤解を生まないよう、事前に簡単な文化紹介コーナーや冊子を配布。
3. 体力や移動への配慮(高齢者)
- バリアフリーな会場を選定。
- 立ちっぱなしにならない設計や、適度な休憩時間の確保。
4. 美術活動の自由度と参加者への配慮のバランス
- 美大生の発想が過激・挑発的になりすぎないよう、目的に沿った表現範囲の確認。
5. 参加目的や期待のズレをなくす
- 事前アンケートやアイスブレイクを通じて、参加者同士の理解を深める。
【人種・文化によって起こりやすいもめごと】
1. 宗教的価値観の違い
- 例:食事の場面での豚肉やアルコールの提供が不快感を招くことも。 → 対策:事前に宗教・食習慣に関する簡単なアンケートを取る。
2. 時間の感覚の違い
- 一部の文化では「時間にルーズ」な印象を持たれることも。 → 対策:ゆとりあるスケジュール管理と「待つこともある」という事前説明。
3. 会話のテンポや遠慮・主張のバランス
- 例:日本人の遠慮が、欧米系留学生には「無関心」に見えることも。 → 対策:話す順番を回すなど、全員が発言しやすい設計を。
4. 外見や服装に関する無意識な偏見
- 高齢者が若者のファッションやタトゥーに驚くなど。 → 対策:多様性を前提とした雰囲気づくり。偏見発言が出た場合は中立にフォロー。
【トラブル予防の工夫】
- 交流のきっかけを用意(例:似顔絵描きあい、食文化紹介、共通テーマのディスカッションなど)
- ファシリテーターの配置:文化や年齢差をつなぐ進行役がいるとスムーズ。
- 小グループ制:大人数だと壁ができがちなので、少人数のワークショップなどを。


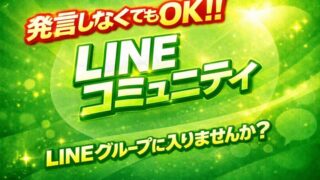






コメント