相続登記(不動産の名義変更)
期限
相続開始から3年以内(期限を超えると過料の可能性あり)
進め方
- 遺言書の確認(公正証書遺言がある場合はすぐに手続き可能)
- 相続人の確定(戸籍謄本を取り寄せて相続関係を整理)
- 遺産分割協議書の作成(相続人全員で話し合い、署名・押印)
- 必要書類を揃えて法務局へ申請(登記申請書、遺産分割協議書、戸籍謄本、固定資産評価証明書など)
相談先
- 司法書士(登記手続きの専門家)
- 弁護士(相続人間で争いがある場合)
注意点
- 2024年の法改正により、期限内に登記しないとペナルティが課される可能性がある
- 共有名義にすると後々の売却が難しくなるため、できるだけ単独名義にするのがよい
相続放棄(借金を引き継ぎたくない場合)
期限
相続開始を知った日から3か月以内
進め方
- 相続財産の調査(プラスとマイナスの財産を確認)
- 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出(戸籍謄本などの必要書類を準備)
- 裁判所の審理を経て相続放棄が認められる
相談先
- 弁護士(借金が多い場合や相続人同士で争いがある場合)
- 司法書士(書類作成の手続きのみ)
注意点
- 3か月を過ぎると自動的に相続したことになる
- 1人が放棄すると次の相続順位の人に相続権が移るため、親族とも相談が必要
相続税申告(財産が基礎控除額を超える場合)
期限
相続開始から10か月以内
進め方
- 相続財産の評価(現金・預貯金・不動産・有価証券などを計算)
- 基礎控除額の確認(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
- 税務署に申告・納税(現金一括払いが基本だが、延納や物納も可能)
相談先
- 税理士(税務計算・申告のプロ)
注意点
- 期限を過ぎると延滞税や加算税が発生
- 配偶者控除や小規模宅地の特例を活用すると節税できる
その他の相続手続き(期限があるもの)
・準確定申告(故人の所得税申告) → 4か月以内
・遺族年金の請求 → 5年以内
・生命保険の請求 → 3年以内
まとめ:誰に相談すればいい?
✅ 相続登記 → 司法書士(登記手続き)、弁護士(争いがある場合)
✅ 相続放棄 → 弁護士(借金が多い場合)、司法書士(書類作成)
✅ 相続税申告 → 税理士(財産評価・税務計算)
✅ 遺産分割の争い → 弁護士(裁判や調停が必要な場合)
相続は期限があるものが多く、早めの対応が必要です。不安な場合は、弁護士・司法書士・税理士の無料相談を利用してみるとよいでしょう。


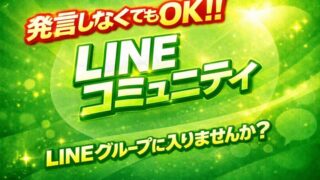






コメント