問題点
① 不動産の共有
相続により不動産を複数人で共有すると、各共有者の権利が等しく発生します。しかし、
共有状態では自由に売却や活用ができないため、管理や処分が難しくなります。
② 共有名義の不動産の売却が難しい
不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
共有者の1人でも反対すると売却ができず、資産の流動性が損なわれます。
③ 固定資産税を代表者が一括して支払う負担
不動産の固定資産税は基本的に共有者全員の負担ですが、実務的には代表者が一括して支払い、後から他の共有者に負担を求める形が多いです。しかし、共有者が支払いに応じないと、
代表者が経済的に負担を背負うことになります。
④ 共有者の増加(世代が進むごとに権利が分散)
相続が続くと、共有者の数が増えていきます。
例えば、親の代では兄弟2人の共有だったものが、その子どもの代には4人、8人と増え、管理や意思決定がさらに難しくなります。
⑤ 意見の不一致
不動産の管理・運用・売却などについて、共有者の間で意見が分かれることが多いです。
特に、遠方に住む共有者や、関心の低い共有者がいると、話し合いが進みにくくなります。
⑥ 共有名義の不動産を分割する際の法的手続きの複雑さ
共有状態を解消するには、不動産を分割(分筆)するか、共有持分を売却・譲渡する必要があります。
しかし、土地の形状や法的制約により分筆できないことも多く、登記変更や税務上の手続きも煩雑です。
解決方法
① 共有者間での話し合い・合意形成
まずは共有者同士で今後の方針を話し合うことが重要です。売却するのか、誰かが単独で所有するのか、賃貸するのかなど、意見をまとめる努力をしましょう。
② 共有者の持分を買い取る
資金に余裕がある場合、1人の共有者が他の共有者の持分を買い取ることで、単独名義にできます。持分の評価額については不動産鑑定士や税理士に相談するとよいでしょう。
③ 共有物分割請求(裁判を利用する)
共有者間で合意できない場合、裁判所に「共有物分割請求」を申し立てる方法があります。裁判では以下の3つの方法が取られます。
- 現物分割:土地を物理的に分割して単独所有にする(分筆)
- 換価分割:不動産を売却し、売却代金を分配する
- 代償分割:1人が不動産を取得し、他の共有者に代償金を支払う
④ 共有持分の売却(第三者への売却)
自分の持分だけを売却することも可能です。不動産業者を通じて市場で売ることもできますし、共有持分専門の買取業者に依頼することもできます。ただし、持分だけでは買い手がつきにくく、価格が安くなる傾向があります。
⑤ 共有者の負担を明確にする契約を結ぶ
固定資産税の支払いなどについて、共有者間で「負担割合」や「支払い方法」を書面で決めておくと、トラブルを避けられます。
⑥ 事前に相続対策をしておく(遺言書・家族信託など)
相続前の段階で、
- 遺言書を作成し、単独相続者を指定する
- 家族信託を利用し、特定の人に管理・処分権限を与える
- 不動産を売却し、現金化して相続する
といった対策を講じることで、共有状態を回避できます。
まとめ
共有名義の不動産は管理や売却が難しく、世代が進むごとにトラブルが増えます。早めに共有者間で話し合い、持分買取・売却・分割請求などの方法を検討することが重要です。相続前の段階で遺言や家族信託を活用するのも有効な対策となります。


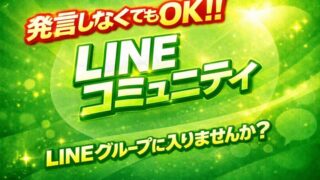






コメント